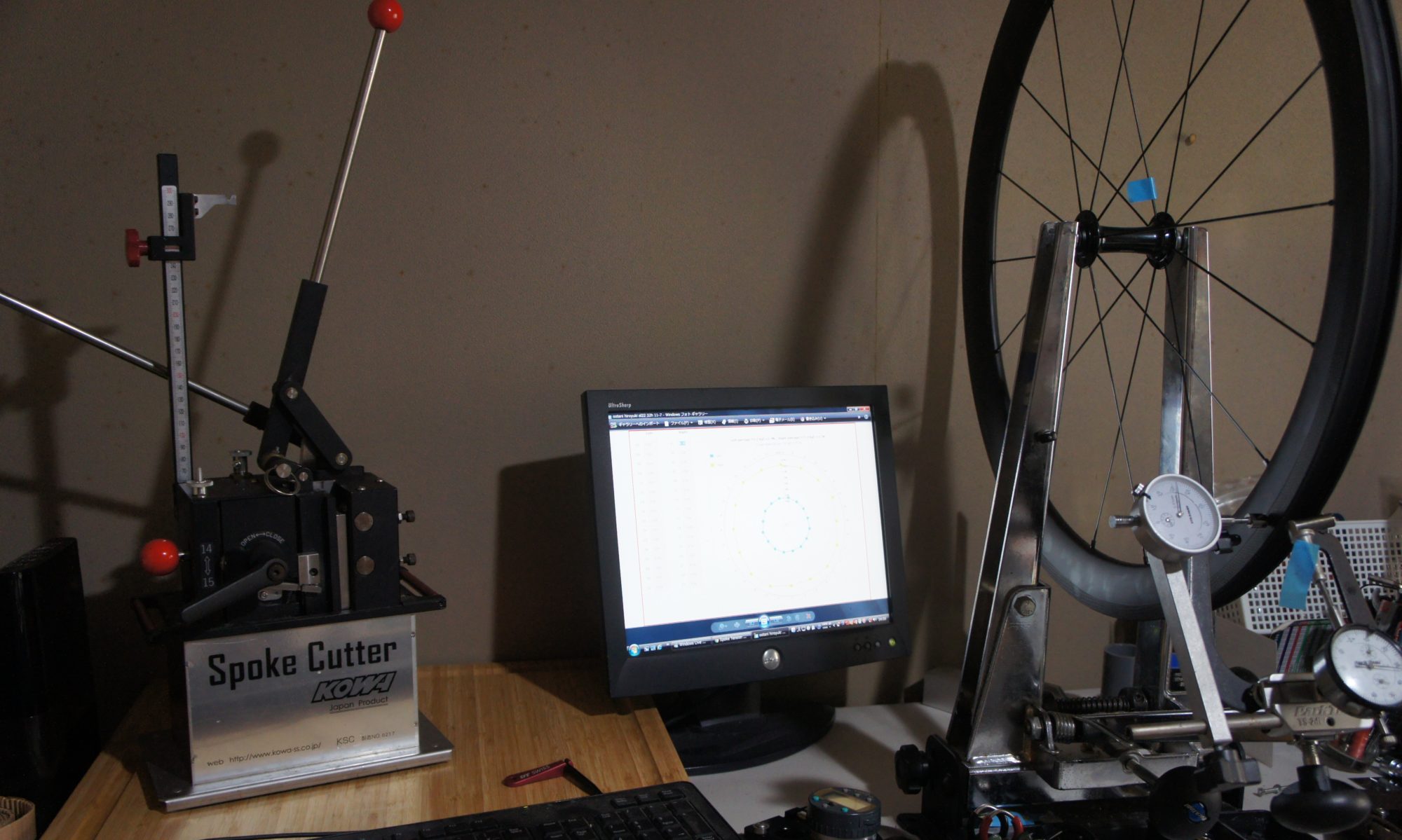ホイール作りを勉強してもなかなか上達しません。先ずしっかりと解説された本が少ないのが現状です。特に日本語で書かれた本はないといってもいいと思います。
英語では

The Bicycle Wheel 3rd Edition

Professional Guide to Wheel Building 7th Edition
体系的にしっかりと解説されたとてもいい本がありますが一般的ではありません。しかし英語の勉強にもなりますのでとてもいい本と思います。
そんな意味でもYouTubでの勉強はとても分かりやすく習得が早いと思います。
視覚に訴えることがとても有効であることはいろんなYouTubから証明されています。
参考になる次のYouTubをお勧めします。
ステイホームで少しでも気が休まるようにと考えられたのか、アメリカのDaveさんがホイールビルダーの秘伝の技を惜しみなく披露しています。
YouTubで下記のタイトルで検索できます。リンクはいたしません。
November Bicycles Wheel Lacing
何気なく見ているとそう作るのかと見終わってしまうのですが、ええええそんなネタを明かしてもエエの?と思うくらいの技を知ることができます。いつもどうするの?と考えている人にはとても良いヒントが隠されています。
作者のDaveさんはできる人はみんなやっていることだという思いなのでしょう。それとも簡単にはできないよという思いなのでしょうか?
見ている人はとても少ないのですが世界中のプロビルダーが参考にしていると思います。