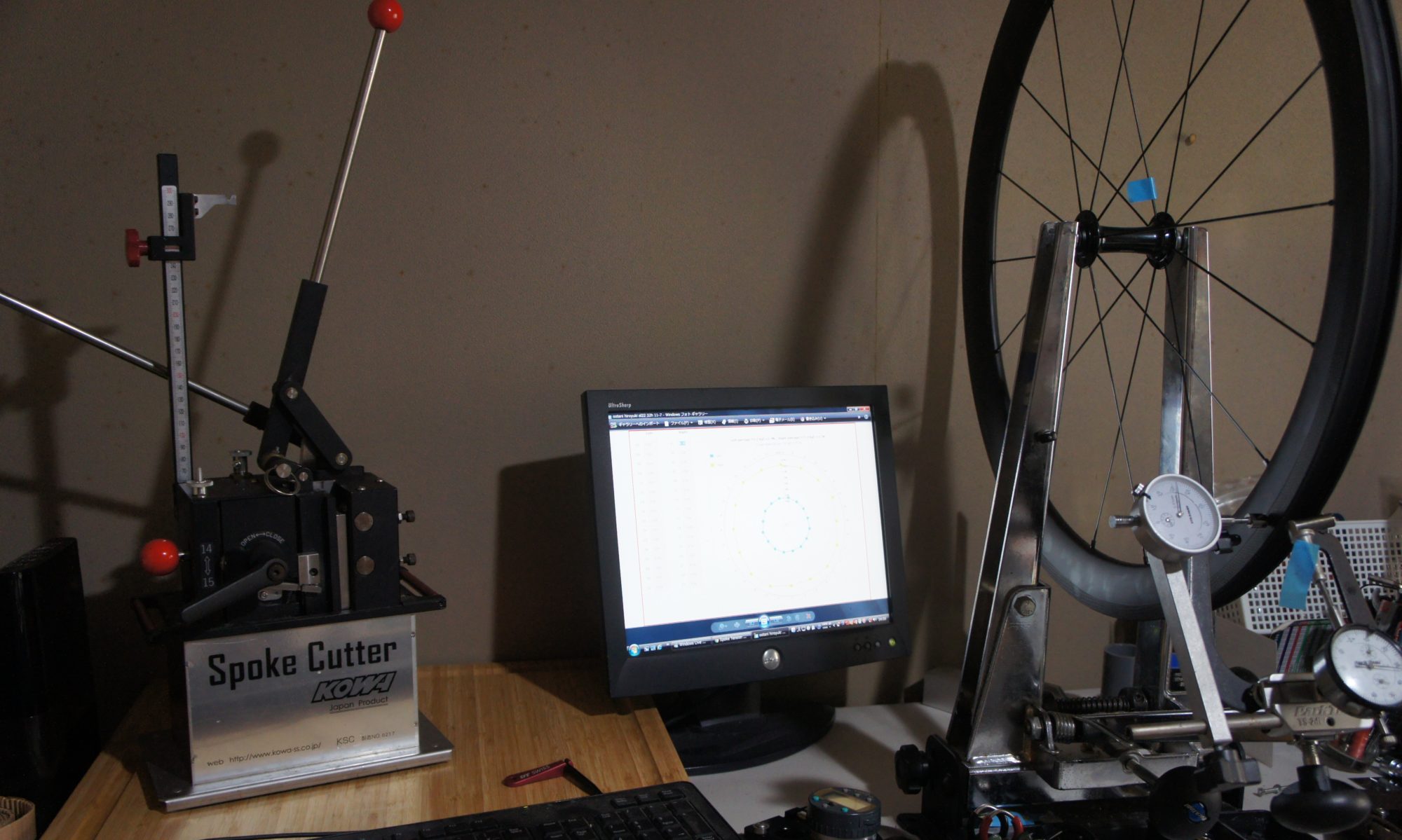ICANのホームページから直接お求めになったホイールの再調整のご依頼いただきホイール分解する機会を得ました。このホイールはとても興味深いホイールです。


ホイールの印象としましてはとても良くできたカッコイイホイールです。価格も手ごろで安価に仕上げるための企業努力を感じます。


前輪Alpha40,後輪Alpha55のスポークはピラーのSA1423というスポークを使われています。スポークのマークはピラーのPマークではありません。ピラースポークの中にリッチマンというブランドがあります。ピラーなのにRマークなのでなんとなく可笑しいです。

このリッチマン・スポークのSA1423は扁平スポークですが扁平部分が2.3/1.5mmというサイズでほとんど丸スポークのような印象を受けます。このスポークはとても剛性が高いスポークで2mmの丸スポークを叩いて扁平にしたようです。このスポークがホイールにプラス面マイナス面で大きく影響していると思います。
ハブは手組ホイールファンでもよく使うノバテックのA291SB,F482SBです。軽量で修理部品が容易に手に入ります。摺動性などハブの性能は必要十分なものを持っています。実用ハブとして価格も安価で、台湾ハブのある意味銘品と思います。


他のホイールと比較して感じるポイントはスポークの選択と考えます。このα40、α55のイメージはシマノホイールの低価格アルミホイールがぴったりと感じました。これは決して悪い意味ではありません。
一般にはシマノWH-RS100のような低価格ホイールは2mmの丸スポークを使っています。入門者用の印象ですが、実は知る人ぞ知る、上級者好みのとてもよく走るホイールです。価格が安価なので完成車に付属するホイールです。
剛性の高すぎるホイールは脚力のない人には使いこなす力がありません。本当はとてもよく走るホイールなのに乗り手とのミスマッチで、重くて走らないという評判が先だってしまいます。実際は剛性が高過ぎるのが理由ですのでとても残念です。
このα40、α55ホイールも全く同じと思います。使われているリッチマンSA1423スポークは扁平スポークですがとても太く2mm丸スポークとほぼ同じです。太いスポーク使われていますので剛性がとても高いホイールです。カーボンリムを使ったシマノRS100という感じです。
このホイールは安価でよく走るでしょう。但し乗り手を選びます。FTP300Wの人なら容易にじゃじゃ馬ホイールを乗りこなせますがビギナーさんではすぐに疲れてしまうのでは?と感じました。乗ってみて最初はいいと感じていてもロングライドには向かないホイールです。
お客様から伺ったお話では予想通りですぐに疲れてしまうホイールでした。解決策を考えようと思います。