XR31T/RT 24/28hホイールをお納めしましたお客様よりインプレメールをいただきました。
体重が約70kgの方です。通常ならホイールのスポーク本数は20/24hのホイールを選ばれるところです。しかし敢えて24/28hのホイールをお勧めしました。

以下お客様からの自己紹介のメールです。新しいホイールの購入を考えられた理由を書かれています。
以下お客様メールの内容です。
少し経緯を書きます。
まだ、ロード初心者で、純正ホイール(リムハイト32mmほどのアルミリム)が2.5kgほどあったので、
もう少し軽快に走りたくて中古のMAVIC キシリウムSRを購入しました。
重量は前後で1kgほど軽くなり、漕ぎ出し・坂は楽になりましたが、乗り心地は悪化しました。
低速な上りは気になりませんが、平坦のアスファルトの段差は頭の芯まで衝撃がくるように感じるほどで脚を緩めてしまう始末です。
また、リムが軽量化されたのと跳ねるのとで速度も以前の2.5kgホイールより落ちてしまい、
上り以外楽しめなくなってしまいました。
回転もいいし、たわまないので上り・ダンシングはキレも良くいいホイールですが、知人のチューブレスに乗せてもらった時にあまりの乗り心地の良さに交換を検討していました。
このような理由でホイールを変えようと考えておられました。
体重と乗られる目的もご連絡いただきました。
体重69kg
平坦6割ヒルクライム4割
25C チューブレス対応
リムハイトは40位希望(優先度低)
前後重量1500g前後以内希望
私がお勧めしましたのが次のホイールです。

前輪
リム キンリン XR31T 24h
ハブ ノヴァテック A291SB 24h
スポーク サピム CX-RAY 黒 ラジアル組
ニップル アルミ
重量 685g リムテープなしで計測

後輪
リム キンリン XR-31RT 3mm オフセット 28h
ハブ ノヴァテック F482SB-11 28h シマノ10速11速兼用
スポーク サピム CX-RAY 黒 2クロス
ニップル アルミ
重量 870g リムテープなしで計測
前後1555g
おススメ理由を述べました。
いろんなベテランの方のご意見を聞いて思うのですがやはりホイールのスポーク数は多いほうがいいということです。24/28hは体重70kg前後の方にはオーバースペックではありません。
理由としては
- 空気抵抗はスポーク8本増えてもほとんど変わりません。
- スポークの多いほうが乗り手の体にやさしいです。地面からの衝撃はスポークの数が少ないほどダイレクトに返ってきます。100km乗った後の疲れは全く違います。
- 各スポークにかかる力が分散できるのでホイール自体にも優しい。スポーク数が多くなればホイールにかかる負荷が減じますのでスポーク折れなどのトラブルが減ります。
- CX-RAYスポークが前後8本増えることになるのですがグラム数で言いますと37,38gです。この重量が増えることによって重くなったと感じる方はいません。おそらく超プロの方でもわからないと思います。ホイールの重量は200g増えてもそんなにわかるものではありません。400、500g変わって初めてわかるものです。
マイナス面
- 見た目がスポーク増えるごとに地味に見えます。私が思いつくのはこれくらいです、マイナスは。
ヒルクライムには軽いほうがいいでしょうが20/24hと比べて40gぐらいの増えても変わりません。スポークが増えて逆にコーナリングは安定します。パワーのある人なら後輪に32hをお勧めするくらいです。
このメールをお送りしましてご納得されお買い上げいただきました。
納品してから約1週間後以下ホイールの感想を聞かせていただきました。
こんにちは。
とりあえず、走れる状態にして50km程走ってみたので初心者ながら感想を書こうかと思います。
見た目は正直シンプルすぎるかなと思いましたが、実際装着してみると全く問題なかったです。
リムハイトもちょうど良く主張しすぎないホイールで気に入りました。
走ってみて、第一印象はとてもスムーズ!
今までがゴロゴロだとスルスルといった擬音が当てはまる感じです。よどみなく回転している感じ。
加速感も良く信号スタートから巡航速度までが楽になりました。
乗り心地ももちろん良くなりました。ガツンときていた段差が角の取れたショックになり、荷重を抜かなくても走り抜けれるようになり思わずにやけてしまいますね。
8~15%くらいの 坂も登ってみました。区間タイム更新です、笑。
しんどさはもちろん変わらないのですが、やはり回転のスムーズさで踏めてしまう感じでした。
平地よりじっくり感触を確かめることができ、バランスがすごく良く感じました。
急勾配でのダンシング中は以前のホイール+タイヤよりリアの空転が目立ちましたが、タイヤが新品のせいかもしれませんね。私のパワーでは剛性不足は感じませんでした。
実走での感想はこんな感じで、とても気に入りました。ますます自転車に乗るのが楽しみになりました。
うれしいご感想いただきました。
体重が70kgぐらいの方はどちらかといえばフロント20リア24hのホイールを選ばれると思います。販売されているホイールは16/20hや20/24hのホイールしか販売されていませんので使われていましたホイールは硬い乗り味のようでした。24/28hホイールは手組ならではの組み合わせです。
手組ホイールはいろんなことができます。汎用部品で作りますので見た目は3G組のようにはいきませんがコスパに優れた走るホイールが出来上ります。 いいタイヤにお金を回せばなお一層よくなります。
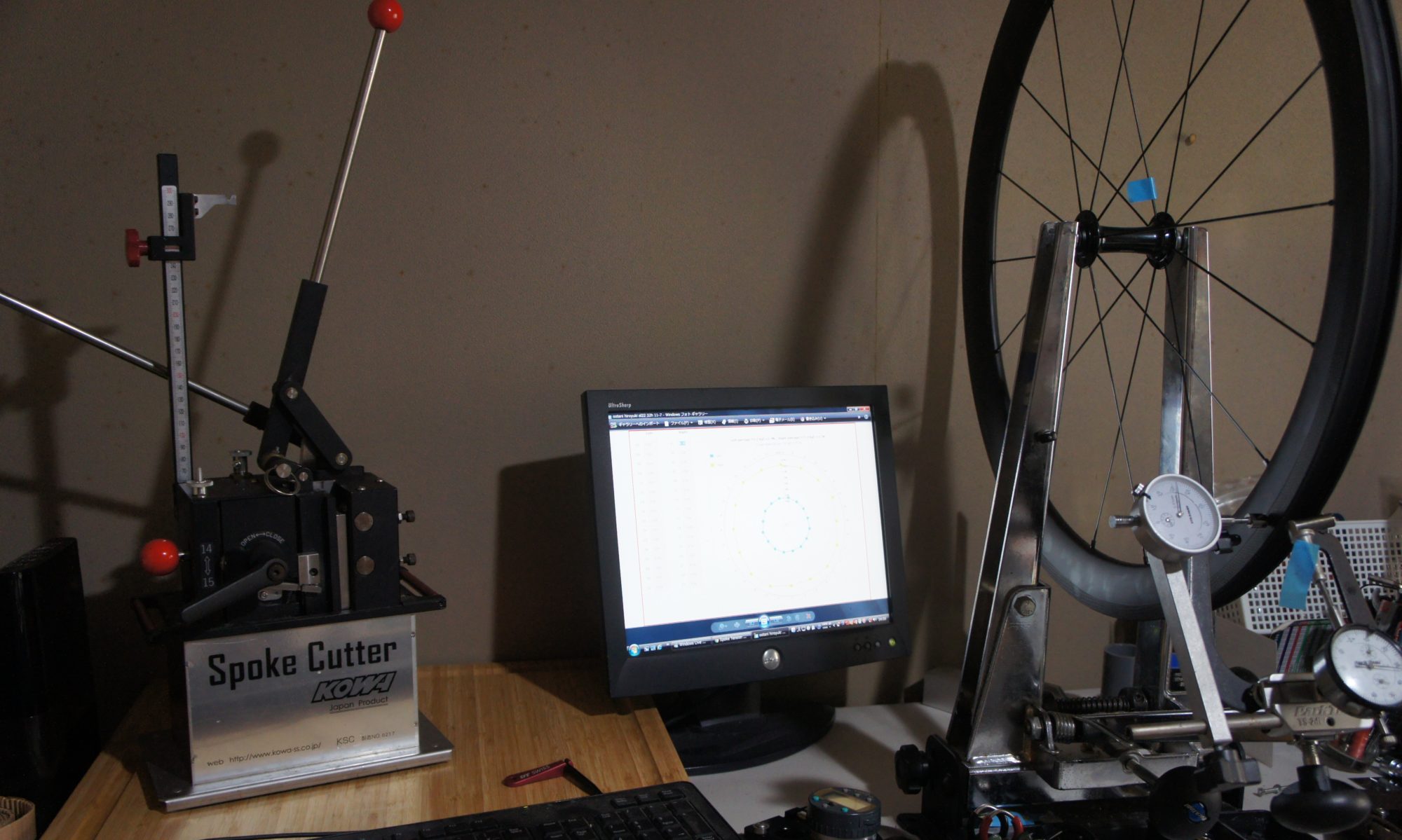


















 フロント18hテンショングラフ
フロント18hテンショングラフ リア24h2:1組テンショングラフ
リア24h2:1組テンショングラフ フロント32h
フロント32h リア32h
リア32h



 フロントテンショングラフ
フロントテンショングラフ リアテンショングラフ
リアテンショングラフ








